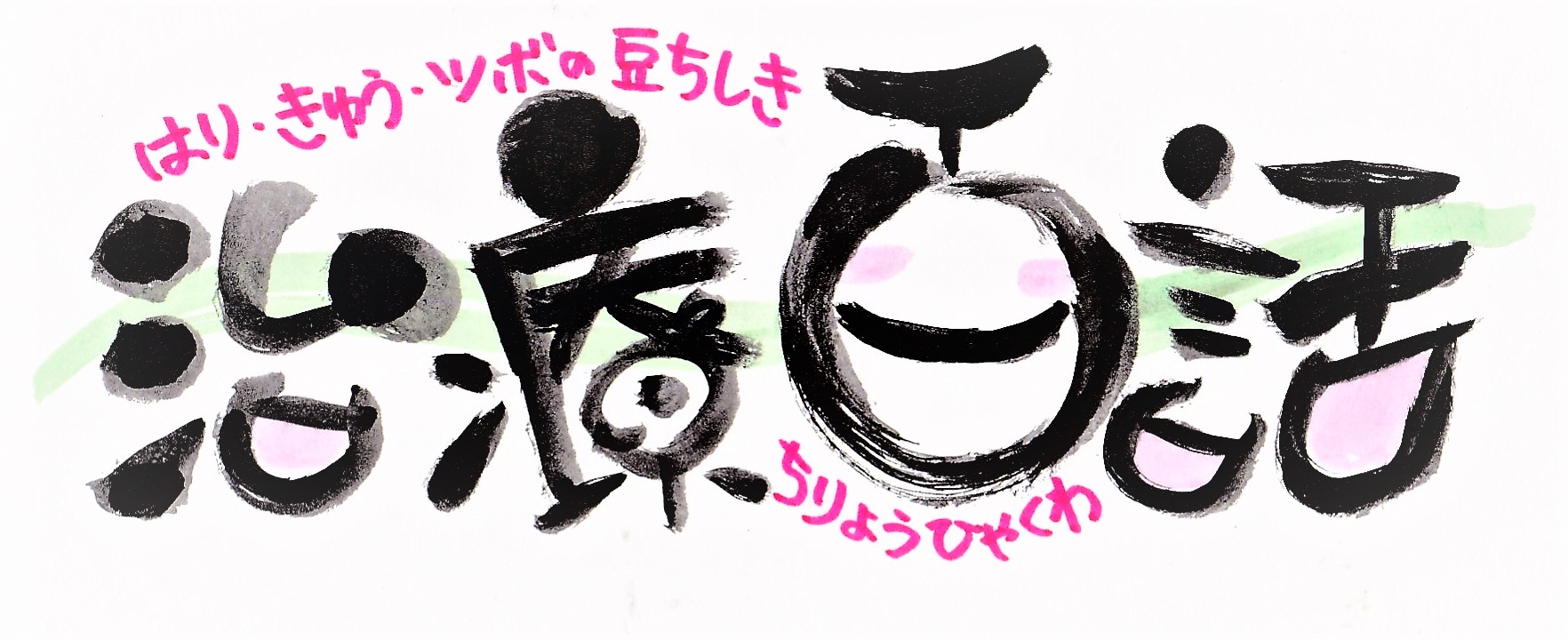昔の風情のある梅雨はいずこ・・・?
ゲリラ豪雨に、激しい気温差。
皆様、ご無事にお過ごしですか。
この季節、服装は薄手の衣服を重ね着して、体温調節いたしましょう。
7部丈やアンクル丈などの丈の短いパンツが流行りですが、東洋医学的には、あまり足首は冷やしたくない箇所。
例えば、足首近くにある【三陰交】というツボ。
冷えからくる婦人科の症状によく使われるツボで、妊婦の時にお灸された方もいらっしゃるでしょう。
どうも最近疲れやすい、更年期かなと思われる方、試しに短いレッグウォーマーを履いてみてください。お灸をすれば尚良し。
雨降りが続くと、気温は高くても身体の冷えの原因になります。
変化の厳しいこの時季を上手に乗り越えましょう。
ブログ一覧
冬ですね~
冬ですね。今朝車窓から富士山がくっきり見えました。
コロナもなかなかしぶといですね。
しかし、こっちだってしぶとくいきますよ!
ヘアブラッシング、鍼、お灸、スクワット、ヨガ、気功、散歩。
気付いた時に、気付いたことを、好きに楽しくやる。
笑う、感動する、時には悲しいドラマで泣く。
これらは、どれも心身の内外を動かすこと、
つまり人間は「動物」なので、動いてないと生きていけないのです。
これらで、ストレスを発散&底力UPして、健康と言う最高の財産を手に入れましょう。
テレワークで1日パソコンやっているあなた、
お子さんに「足の裏フミフミ(足の裏を踏んでもらう)」してもらいましょう。
スクワット(膝が前に出すぎないように)も良いですよ。
冷えは万病の元!!
昔は「風邪は万病の元」と言いましたが、私は「冷えは万病の元」と思っています。
人間は動物です。身体を動かし、活動することによって生かされるようにできています。
ここでいう「冷え」とは、「寒い所に薄着でいたので鼻水が出た」といったことだけではありません。
心理的に苦しいことがあっても「冷え」ます。
これは西洋医学で見ても、いわゆるストレスホルモンと呼ばれるのが増えたり、胃腸の機能や体温などを司る自律神経が乱れたり。
結果的にその人の弱い所に影響を及ぼし、何らかの不具合が生じたりするのです。
特に女性は、子どもを産むため、脂肪が多く(脂肪はいったん冷えると温まりにくい)、又、生理により毎月多量の血液を排出しなければなりませんし...
スマホ、PCによる目の酷使、
運動不足(けっこうやってるよーという方の中には、その後のケアが足りず、むしろ筋肉をいためていたり。まあ、過ぎたるはなんとやらと、便利は必ずしもためならず、かもしれません)、
食生活の乱れや人間関係。
コロナで会いたくない人の誘いにエクスキューズが出来て助かった方もいるでしょうが、やはり人と関わらないと生きていけないなと実感しました。
急に全て解禁も不安が残りますが、まずは会いたかったあの人と鎌倉散策でよく歩き、おいしいランチでも如何ですか?
2021.11.18 福嶋美奈子先生
たしかに“弱点”=“ネック”
地球温暖化のせいか、日本の四季もくずれて、激しい気温・気圧差になかなか身体もついていくのが大変ですね。
おかげで右を見るとTシャツ姿、左を見るとダウンをはおっているという不思議な光景に出くわすことも。
昔は「衣替え」なんてことがありましたが、今は自分の身を守る観点からは、薄着を着重ねるのが利口かもしれません。
そんな時、私が語るのは「三首」。
首・手首・足首。
若いころと比べて体型が気になる大人の人がきれいに見える為には、この「三首」を見せて!と、どの本にも書いてあるのですが、それを見る度にキャーと叫びたくなる私(笑)。
よく弱点を”ネック”とよんだりしますね。
つまり、この「三首」は弱点となり得る部位。
“冷え”もこの「三首」から入りやすいのです。
スカーフ1枚、短いレッグウォーマーなど、かさばらない物をジップロックに入れてカバンに入れておきましょう。
2021.11.5 福嶋美奈子先生
新しいスタートに!!
新入学等、新しいスタートを切られた方、まずはおめでとうございます。
気合が入り過ぎて息切れしないように、力んでいるなと感じたら、ゆっくり息を吐きましょう。
さて、事初めてして、“鍼灸”とは、どんなものか少しお話しましょう。
私たち鍼灸師は、「はり師」「きゅう師」という2つの国家資格を持つ「医療従事者」になります。
「はり、きゅう」と聞くと「イタイ、アツイ」と連想してしまいますが、今でも注射の苦手な私、昔は敬遠していました。しかし受けてみてびっくり!!
「痛くないし、熱くない」と言うか「むしろ気持ち良い」
で、鍼灸師になっちゃいました。
日本の「鍼(はり)」は、工夫満載でやさしい。更に敏感な人用に「刺さない鍼」もあります。代表的な物では「子供用の鍼」。「もっとやって!」とせがまれることもしばしば。私自身は、鍼灸師として「気持ち良い」を目指しているので、お灸もじんわり、ぽかぽか。
辛いのにでも病院に行くほどでもないと、我慢しているあなた、ものは試し、一度トライしてみては?
2021.4.17 福嶋美奈子鍼灸師